(2002年5月3日〜6日・3泊4日)
| 東雲のGW北紀行・十勝後志縦横無尽 (2002年5月3日〜6日・3泊4日) |
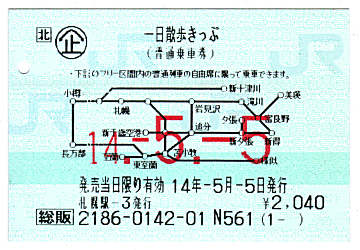 肉や野菜はなかったけれど、腹ごしらえが済んでひと息。部屋に戻ってきたが、実は今日の行き先が定まっていない。夕方T君と合流し、サッポロビール園でジンギスカンと生ビールを飲み食いするということだけで、昼間の予定は白紙。一応、『道内時刻表』の中に載っている「一日散歩きっぷ」(写真右→)を使うことは、なんとなく決まっている。JR北海道から出ているフリーきっぷで、土休日・夏休み期間の一日に普通列車乗り放題で2,040円という、首都圏でいう「ホリデーパス」と同じ商品。なぜか、「一日散歩きっぷ」も「ホリデーパス」も、手元の大型版『JR時刻表』には載っていない。『JTB時刻表』よりもJR寄りなのに、なぜだろう。
肉や野菜はなかったけれど、腹ごしらえが済んでひと息。部屋に戻ってきたが、実は今日の行き先が定まっていない。夕方T君と合流し、サッポロビール園でジンギスカンと生ビールを飲み食いするということだけで、昼間の予定は白紙。一応、『道内時刻表』の中に載っている「一日散歩きっぷ」(写真右→)を使うことは、なんとなく決まっている。JR北海道から出ているフリーきっぷで、土休日・夏休み期間の一日に普通列車乗り放題で2,040円という、首都圏でいう「ホリデーパス」と同じ商品。なぜか、「一日散歩きっぷ」も「ホリデーパス」も、手元の大型版『JR時刻表』には載っていない。『JTB時刻表』よりもJR寄りなのに、なぜだろう。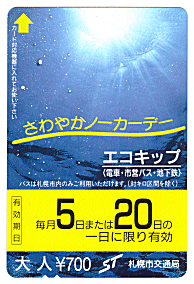 発泡酒をちびちび飲みながら、夕張へ行こうか、富良野にしようか、どうせなら両方行こうか、などとあれこれ考えていたのだが、改めて『道内時刻表』をひっくり返しながら、倶知安・余市方面へ行ってみることに決めた。札幌から小樽までは電化されていて、1時間に4本くらい列車があるのだが、小樽から先は列車本数が激減するので、来た電車に乗ってというわけにはいかない。午前中に小樽から倶知安へ行く列車は、6:11、8:07、9:43、11:21。小樽9:43発に間に合う列車は、札幌8:41発。札幌駅で切符を買う時間も必要なので、8:15あわてて宿を出て、地下鉄東豊線・豊水すすきの駅へ向かった。
発泡酒をちびちび飲みながら、夕張へ行こうか、富良野にしようか、どうせなら両方行こうか、などとあれこれ考えていたのだが、改めて『道内時刻表』をひっくり返しながら、倶知安・余市方面へ行ってみることに決めた。札幌から小樽までは電化されていて、1時間に4本くらい列車があるのだが、小樽から先は列車本数が激減するので、来た電車に乗ってというわけにはいかない。午前中に小樽から倶知安へ行く列車は、6:11、8:07、9:43、11:21。小樽9:43発に間に合う列車は、札幌8:41発。札幌駅で切符を買う時間も必要なので、8:15あわてて宿を出て、地下鉄東豊線・豊水すすきの駅へ向かった。
 春スキーの名所・ニセコアンヌプリや、“蝦夷富士”こと羊蹄山が見えてきて、後志支庁所在地[倶知安]に到着。かつては、羊蹄山の東麓から喜茂別・大滝を経て伊達紋別に至る“胆振線”の分岐駅だったが、国鉄分割民営化直前の昭和61(1986)年10月末に廃止され、現在ではただの中間駅である。駅前はニセコ・積丹方面、留寿都・洞爺湖方面へのバスターミナルになっており、ロータリーの中央部は駅まで車で来る乗客のための駐車場になっている。駅舎を出て左手の一角に、羊蹄山からの湧き水が飲めるようになっており、一口のどを潤す。
春スキーの名所・ニセコアンヌプリや、“蝦夷富士”こと羊蹄山が見えてきて、後志支庁所在地[倶知安]に到着。かつては、羊蹄山の東麓から喜茂別・大滝を経て伊達紋別に至る“胆振線”の分岐駅だったが、国鉄分割民営化直前の昭和61(1986)年10月末に廃止され、現在ではただの中間駅である。駅前はニセコ・積丹方面、留寿都・洞爺湖方面へのバスターミナルになっており、ロータリーの中央部は駅まで車で来る乗客のための駐車場になっている。駅舎を出て左手の一角に、羊蹄山からの湧き水が飲めるようになっており、一口のどを潤す。 また後志支庁前を通って、倶知安駅前の十字街から国道5号線に入る。ニセコアンヌプリを左手の車窓に見ながら、倶知安峠を越えれば、倶知安の北隣の共和町に入る。山あいから少し開けて、民家がぽつぽつ点在する中、11:20 頃[ワイス温泉前]で下車。国道沿いに立っている地名標示板には 「ワイス/Waisu」 とある。観光マップには、ニセコ山系の北端に“ワイスホルン”という、管楽器みたいな名前の山(標高1046m)がある。エーデルワイスと関係あるのだろうか。
また後志支庁前を通って、倶知安駅前の十字街から国道5号線に入る。ニセコアンヌプリを左手の車窓に見ながら、倶知安峠を越えれば、倶知安の北隣の共和町に入る。山あいから少し開けて、民家がぽつぽつ点在する中、11:20 頃[ワイス温泉前]で下車。国道沿いに立っている地名標示板には 「ワイス/Waisu」 とある。観光マップには、ニセコ山系の北端に“ワイスホルン”という、管楽器みたいな名前の山(標高1046m)がある。エーデルワイスと関係あるのだろうか。 なんとすでにいい湯加減のお湯が出ていた。サービス過剰じゃねーか。……とにかく、ちょうどいいお湯と持参の石鹸で身体を洗い、湯船に入る。無色透明で格別な匂いがしない温泉にしばらくつかり、いったん上がってまた赤い蛇口からお湯を出そうとすると、こんどはぬるいお湯しか出てこない。青い蛇口をひねらないのに、桶にたまるお湯はぬるくなる一方。もはや、ちょうどよい温度のお湯は、湯船の中の温泉しかなくなってしまった。これは、客が少ない時間帯でボイラーを切ってあるためなのか。一人だけ使ってこのありさまなのだから、早朝や夜にたくさんお湯を使うときは、果たしてどうなのか。全くもって心配せずにいられない。
なんとすでにいい湯加減のお湯が出ていた。サービス過剰じゃねーか。……とにかく、ちょうどいいお湯と持参の石鹸で身体を洗い、湯船に入る。無色透明で格別な匂いがしない温泉にしばらくつかり、いったん上がってまた赤い蛇口からお湯を出そうとすると、こんどはぬるいお湯しか出てこない。青い蛇口をひねらないのに、桶にたまるお湯はぬるくなる一方。もはや、ちょうどよい温度のお湯は、湯船の中の温泉しかなくなってしまった。これは、客が少ない時間帯でボイラーを切ってあるためなのか。一人だけ使ってこのありさまなのだから、早朝や夜にたくさんお湯を使うときは、果たしてどうなのか。全くもって心配せずにいられない。
《※9》地下鉄4回・バス2回で1,040円分……ふつうなら200円×6=1,200円となるのだが、市バス・地下鉄には乗継ぎ運賃が設定されており、地下鉄1区(=初乗り)とバス市内均一区間の乗り継ぎは320円となっている。地下鉄の券売機でバス乗継ぎ券を売ってるし、下車時に自動精算機で追加運賃を払えばバス乗継ぎ券を発行してくれる。バスなら下車時に「地下鉄乗り継ぎ」と申し出て320円を払えば、地下鉄1区乗継ぎ券が出てくる(地下鉄を2区以上乗る場合は、下車時に乗り越し精算)。さらに、市営交通のストアードフェアシステム「ウィズユーカード」なら、自動的に乗継ぎ運賃で計算してくれる。
……こういう、電車・バスの乗り継ぎ割引は、関東ではほとんど見られない。都営交通にしても、連絡定期券が10%引きなのと、都バス同士の乗り継ぎで100円引きになる「都営バス専用乗継割引カード」をひっそり売っているだけである。
《※10》キロポスト……鉄道の線路の脇に立っている標識の一種で、その路線の起点からの距離を示す“距離標”のこと。1km単位・500m単位・100m単位で形状が異なるが、いずれにしても車両の床面よりも低いから、草むらごしには見えない。そういえば高速道路や国道や都道にもキロポストはあるけど、それをいちいち気にしながら運転する人はあまりいないだろう。
| 【5/5】その2・余市からビール園へ | |